
4つのボディタイプからなる16代目クラウン。今回はエステートの評価ドライバーとエンジニアに密着!30回ものダメ出しが、もっといいクルマづくりにつながる!?

4つのボディタイプを展開する新型クラウン。それぞれのモデルは、クラウンネス(=“静粛性” “快適性” “上質さ”)と称される、歴代クラウンによって培われてきた乗り味が追求されている。その一方で、それぞれのモデルには各ボディタイプならではの異なるキャラクターも与えられている。
こうしたクルマの味づくりで重要な役割を果たすのが、評価ドライバーだ。トヨタイムズでは、クルマの乗り味がいかにつくられるのかを明らかにすべく、クラウン シリーズ各モデルの開発に携わった評価ドライバーとエンジニアを取材。今回は、エステートにおける“乗り味づくりの現場”に迫る。
ロングドライブでも疲れない
「機能的なSUVとしてアクティブライフを楽しめる、ワゴンとSUVの融合」と謳われるクラウン エステート。

「クラウン シリーズの4つのボディタイプのなかで、最も機能性を重視したモデルです」
そう語るのは、クロスオーバー、スポーツ、そしてエステートの製品企画主査を務めた本間裕二だ。
本間

お客様に使っていただきたいシーンでいうと、ご家族や友人と多くの荷物を積んで長距離を移動し、旅先で思い切り楽しんでいただく、そんなクルマに仕上げたいと考えました。
そのため、いかに疲れずに、ロングドライブを楽しんでいただくことができるかを目指して、開発チームのメンバーとともにつくり込んでいきました。
凄腕技能養成部の評価ドライバーで、クラウン シリーズ全体の開発支援に携わった片山智之は、ロングドライブでも疲れない走りを実現させるために、直進安定性にこだわったと語る。
片山
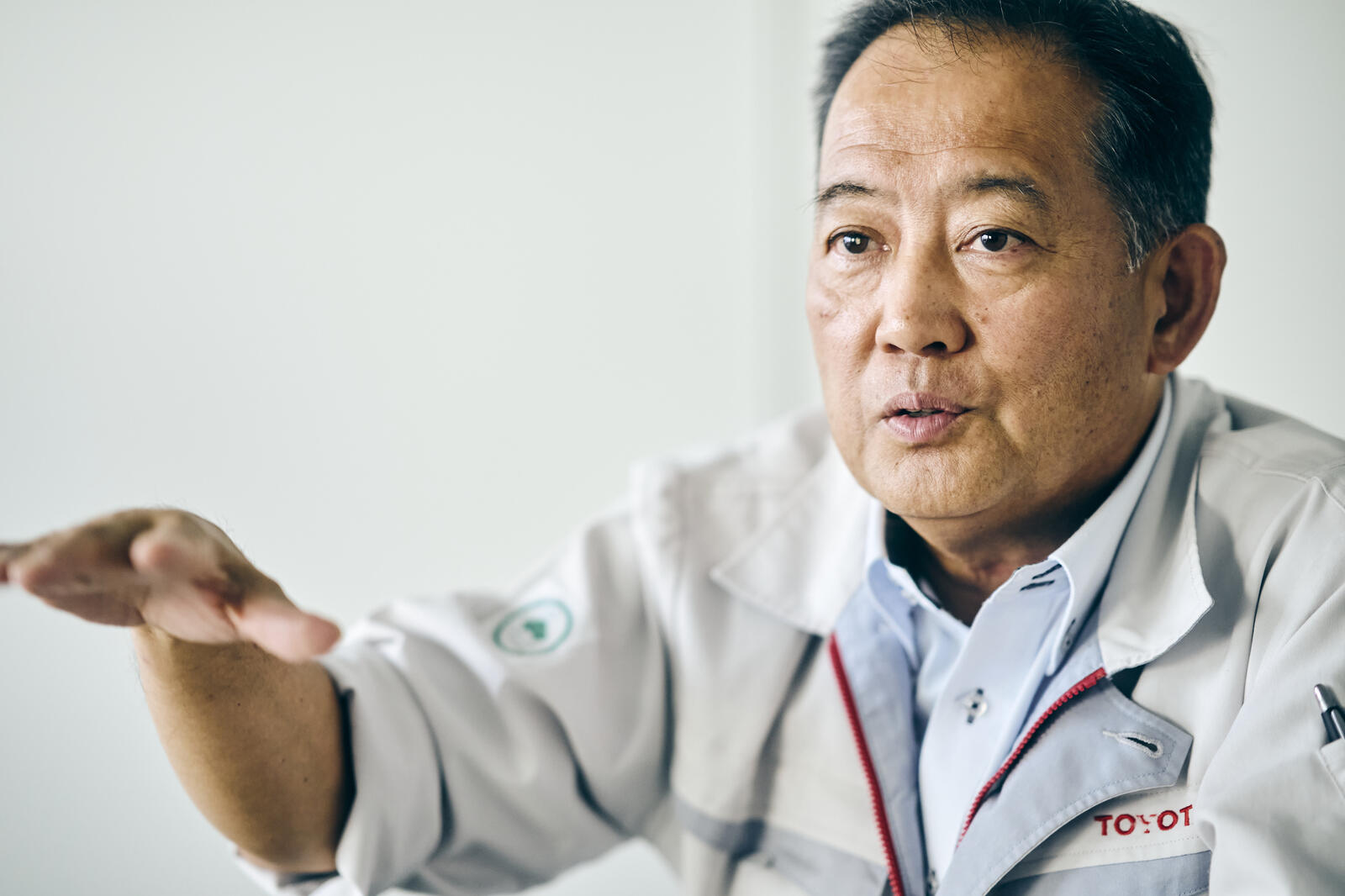
クロスオーバーやスポーツのときにも話しましたが、走り出しから20km/hくらいまでのクラウンならではの上質な乗り味は、エステートでもこだわりました。
そのうえで直進安定性、つまり、いかにまっすぐ走るかという部分について、4モデルのなかでも特化して追求しました。
そもそもすべてのトヨタのクルマが、お客様に安心して乗っていただけるよう直進安定性の良さは必須項目として開発されています。
エステートでは、よりその部分をしっかり感じていただけるような乗り味を目指しました。
本間
SUVのように車高の高いクルマは、高速道路でトラックの横を通過するときなどに横風の影響でボディが揺れやすいです。すると、ドライバーは無意識に修正舵を当てるのですが、ロングドライブではこれが疲れの原因になります。
そこで、とにかくどっしりと安定して、矢のようにまっすぐ走れるクルマに仕上げたいと考えました。
運転しても楽しいクルマを目指して
その一方で、ドライバーズカーとしての走りの楽しさも大切にしたかったという。
片山
直進安定性だけを追求すると、ワインディングロードなどでドライバーのイメージした通りに気持ち良く曲がってくれないクルマになってしまいます。
乗心地の良さと直進安定性、そして気持ちのいいコーナリング。これらのバランスを図ることが重要になります。
車種担当評価ドライバーとしてクロスオーバーとエステートの開発に携わった、車両技術開発部の西野淳も、気持ちのいいコーナリングを意識してつくり込みを行ったという。
西野

どっしりと安定しながらも、ドライバーズカーとしての運転の楽しさも損ないたくないと考えました。
そこで、片山さんのイメージを元に、サスペンションのバネレート、ショックアブソーバーの減衰力、スタビライザーの強度、さらにはDRS(後輪操舵システム)やEPS(電動パワーステアリング)といった電子制御アイテムを少しずつ調整しながら、最適な乗り味を探りました。
同じく車両技術開発部の車種担当評価ドライバーである伊藤宗一は、EPSのチューニングに苦労したという。
伊藤

EPSを重めにチューニングすると、どっしり感のある走りを演出しやすいです。
一方で、ステアリングが重いと、どうしてもドライバーは切り遅れてしまいます。すると、切り遅れを補うためにステアリングを早く切ることになり、結果的にクルマの動きがぎくしゃくします。
そういった性能のバランスを仕上げる場面では、片山さんと一緒に微調整を繰り返して、ステアフィールとクルマの動きが合致する最適なチューニングを探りました。
こうして開発チームのメンバーは、クロスオーバーとスポーツで得られたノウハウを活かしながら、エステートとしての乗り味をつくっていった。
シャシー設計を担当したMSプラットフォーム開発部のエンジニア、西川優はコーナリング時の自然な動きについては、クロスオーバーをベンチマークとしたという。
西川

実は、クロスオーバーよりも車高が25ミリ高く 、ワゴンボディでリアがより重いエステートを、クロスオーバーと同じような動きに仕上げること自体がチャレンジでした。
特に、コーナリング時に自然なロールを感じながら曲がっていく動きを実現させるのが難題でした。サスペンションチューニングだけでは、どうしても直進安定性とトレードオフの関係になってしまいます。
そこで、ボディ形状含めたクルマ全体でこのバランスを取っていく議論を開始しました。
直進安定性と自然なロール感を両立するために採用した空力デバイスにも、クロスオーバーやスポーツからのノウハウが活かされていると、操縦安定性や乗心地の開発に携わった車両制御開発部のエンジニア、岩田拓也は話す。
岩田

トヨタではサイドミラーの付け根部分やリアコンビネーションランプをフィン形状にして直進安定性を向上させているクルマが多いです。
ところが、今回はデザインチームからリアコンビネーションランプなど意匠部分に空力処理を施すことを避けたいとの相談がありました。
そこで、人目に触れないアンダーフロアに凹凸形状の整流パネルやフィンを装着することで対応しました。

クルマがカニ走り!?
直進安定性と気持ちのいい走りの両立という難題以外にも、開発チームは大きな壁に突き当たった。そのひとつが「リアコンフォートモード」の適合だった。
リアコンフォートモードとは、「スポーツ」「コンフォート」といったドライブモードのひとつで、後席の快適性を重視したモード。
具体的には、上下運動をAVS(電子制御サスペンション)で、横方向の揺れをDRS(後輪操舵システム)で制御することで、後席乗員の体が揺れるのを防ぐ。
「リアコンフォートモードは、高速道路でのレーンチェンジやランプウェイなどで効果を発揮するんです」と、クラウン シリーズにおけるシャシーの性能設計開発リーダーを務めた、MSプラットフォーム開発部のエンジニア、松宮真一郎は話す。
松宮

DRSは低速域で後輪を逆位相に切って取り回し性を向上させ、60km/h以上では同位相にステアすることで走行安定性を高める電子制御アイテムです。
リアコンフォートモードでは、高速域で同位相への切れ角を通常よりかなり増やします。すると、車両が斜め前方にカニ走りするような動きになるので、横揺れが抑えられます。
ただ、ドライバーにとっては違和感があるということで、片山さんからは厳しいフィードバックをいただきました。
片山

例えば、高速道路でレーンチェンジする際に、普通はフロント、リアとボディが自然にロールしながら曲がっていくのですが、当初のリアコンフォートモードではフロントとリアの動きがちぐはぐで、かなり不自然な動きになっていました。
後席の子どもやお母さんが快適でも、運転しているお父さんが疲れちゃうようなモードではダメだと伝えました。
チーム内では「採用を見送った方がいいのでは」という声もあがった。ただ、すでに同モードのソフトウェア開発にかなりの熱量を注いでいたため、実装までやり切りたかった、と松宮はいう。
松宮たちシャシー設計担当者の思いを受け、伊藤、西野の2人の車種担当評価ドライバーは、何とかカタチにすべく、適合に取り組んだという。
西野
私たちとしては、リアコンフォートモードの可能性を感じていたので、とにかくお客様に喜んでいただけるレベルまで引き上げようという思いで走り込みを行いました。
時間をかけて適合して、片山さんに乗ってもらうと「曲がる部分の違和感は解消されたけど、今度は直進安定性がダメだ」というフィードバックを受けました。そこから30回くらい適合をやり直して、やっと承認をもらえました。

最終的には、後席は揺れが少なく快適で、ドライバーにとって違和感のない乗り味が実現できた。
伊藤や西野の上司である車両技術開発部の館郁夫組長は、開発車両の適合で片山から承認を得るまでに、これほど長い時間を要したのは初めてだと語る。
館

通常は1、2回の確認で承認がでるのですが、今回はよく最後まであきらめずに粘り強く適合に励んでくれたと思っています。
これも、私たち車種担当評価ドライバーのチームは、これまでの経験から、片山さんたち凄腕技能養成部の監査メンバーとの信頼関係が築けており、「もっといいクルマをつくろう」という共通の目的意識に立てているからこそだと思います。
今回、エステートの開発を通して、片山をはじめとする評価ドライバーがつくり上げた成果をデータ化し、次の開発に活かすのがエンジニアの使命だ。
すでにクロスオーバーの改良型には、後発のスポーツやエステートの開発で得られたノウハウが活かされている。
こうした評価ドライバーとエンジニアによる、たゆみない共創が、これからもクルマを進化させていく。
