
突然、半身不随になることは誰の身にも起こりうる。だからこそ"あるロボット"の利用者が増えているという。
感動的な話が生まれるリハビリ支援ロボットだが、医師や療法士が今もトヨタに伝えている改善要望はなんと100件を超えるという…
療法士の負荷も大きく減らせる
医療現場でも一般的になってきたリハビリ支援ロボット。ただし、日本と海外では考え方に違いがあるという。
七栗記念病院 平野哲先生
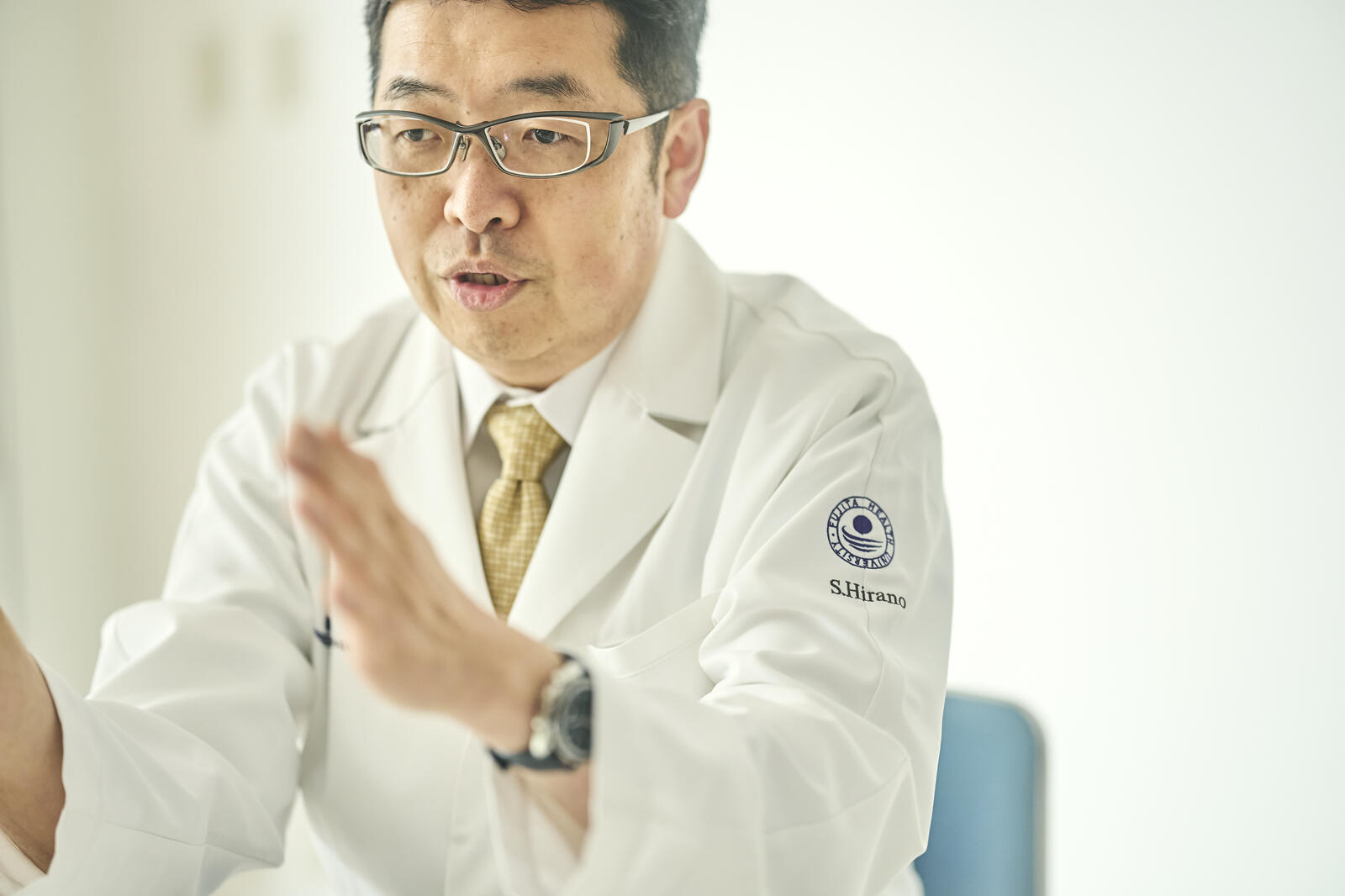
海外のものは強制的に歩かせるものが多いですが、このロボットの開発を先導してきた才藤栄一教授は、”運動学習理論”に基づいたリハビリを提唱してきました。
簡単にいうと、人全体を“ひとつのシステム”と考えて、良いパーツをうまく使いながら、病気前とは違う新しい動作にチャレンジする考えです。
一人ひとりの状況に合わせて回復を目指す“人中心”のロボットというわけだ。
七栗記念病院 理学療法士 冨田憲先生

ロボットの活用で、療法士は身体的な負担を減らせるだけでなく、患者さんの歩行を多角的かつ客観的に分析することが可能になりました。
また、さまざまなパラメータを調整することで、個々の患者さんに適した練習条件を容易に設定できるようにもなっています。
同僚には「私たちは“練習のデザイナー”として、より効果的なリハビリテーションを創り上げていこう」と伝えています。
リハビリ支援ロボットは改善が繰り返され、2024年12月に最新型が完成。トヨタで開発を手掛けるメンバーに何が進化したかを聞いてみると…
新事業企画部 ヘルスケア事業室 河田則彦グループ長

大きな特徴は、足に取り付けるロボットの軽量化です。片側の足に装着するロボットにセンサーが付いていましたが、それを床面に移動。すると軽量化だけでなく、装着していないほうの足、つまり両足の荷重もわかるようになりました。

半身不随の患者さんだけでなく、あらゆる人の歩行練習に活用できる可能性が生まれたわけです。
新事業企画部 ヘルスケア事業室 中村卓磨グループ長

ソフト面では、異常歩行検知の機能を高めることも病院側から依頼された使命でした。何をもって異常として検知するのか、先生たちの意見を逐一聞きました。
結果的に13種類もの異常歩行の検知ロジックを刷新すると共に、重症度の判別を3段階から5段階に詳細化しました。バージョンアップというより、新しいものをつくったような感覚です。
他にも、装着する際のサイズ調整がラクになったり、ロボットのフレームを減らし、より自然な歩行ができるようになった。
「トヨタさんには、常に100件くらい改善要望を出しています」と平野先生。それに対しトヨタ側は「いや、500件は依頼されています」と笑顔で訂正。改善に終わりはない。そう感じられるやり取りだった。

このロボットを卒業したらどうなるの?
*(仮称):KNee Extension Assist Robot
ある程度歩けるようになり歩行練習をしていると、急にガクッと膝から崩れ落ちる「膝折れ」という危険な状況が起こることがあるという。

KNEARは麻痺のある膝に装着。体重を支えるときには油圧ロックで崩れ落ちを防ぎ、歩こうと膝を曲げるときはセンサー制御で油圧ロックを解除し、抵抗なく膝を屈曲できる仕組みだ。
実証実験でも「歩くときに体重をかけることが怖かったが、これがあると安心して歩ける」という声が。
新事業企画部 ヘルスケア事業室 西田陽

膝の角度や地面との傾きもコントロールして歩行をサポ―トできます。データも取れるので解析・フィードバックも可能です。
大型機器と違って低価格で多くの人に届けられるので、小さな病院でも使用できる可能性が大きく、発売に向けて開発を続けています。
トヨタのリハビリ支援ロボット。その裏には「すべての『行きたい』を叶えていきたい」という想いがあるのだ。
困っている人がいる限り、あきらめる訳にはいかない。さらなる進化を目指してトヨタの取り組みは続いていく。

