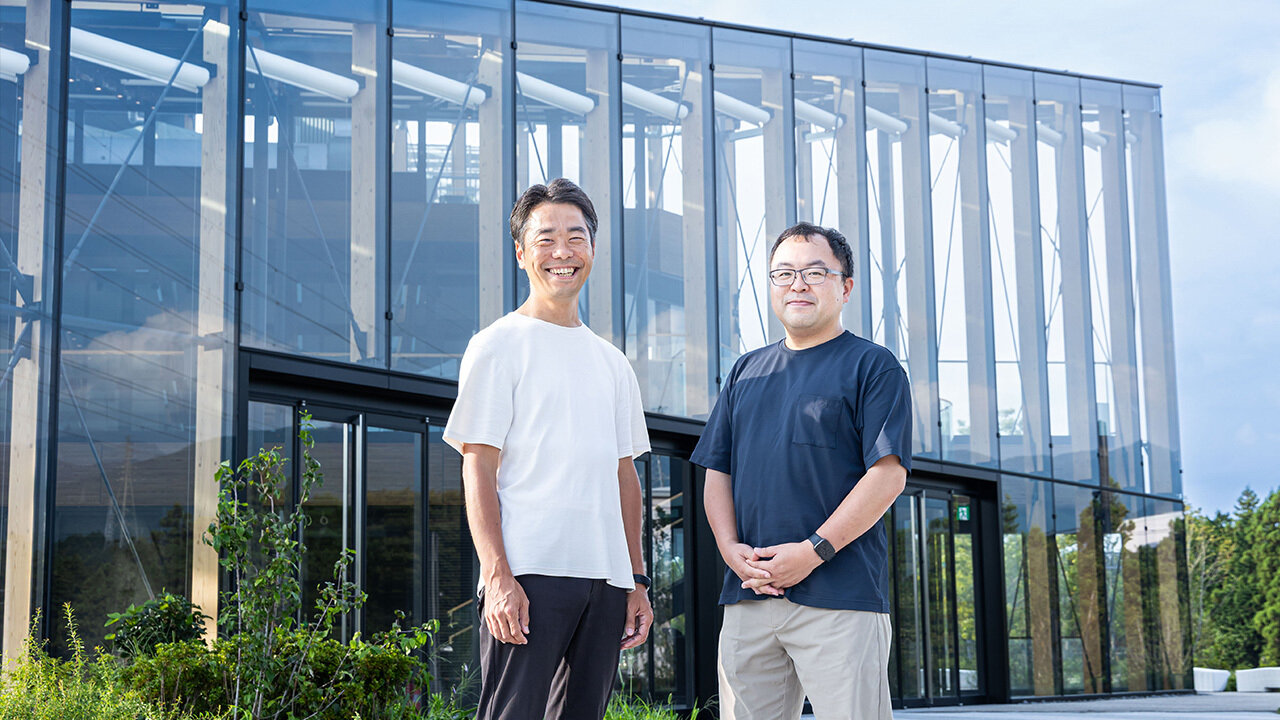
「実証実験の街を使い尽くし、誰も想像しない未来をつくる」。そんな仲間の募集が始まった。「ウーブンシティ・チャレンジ」とは?
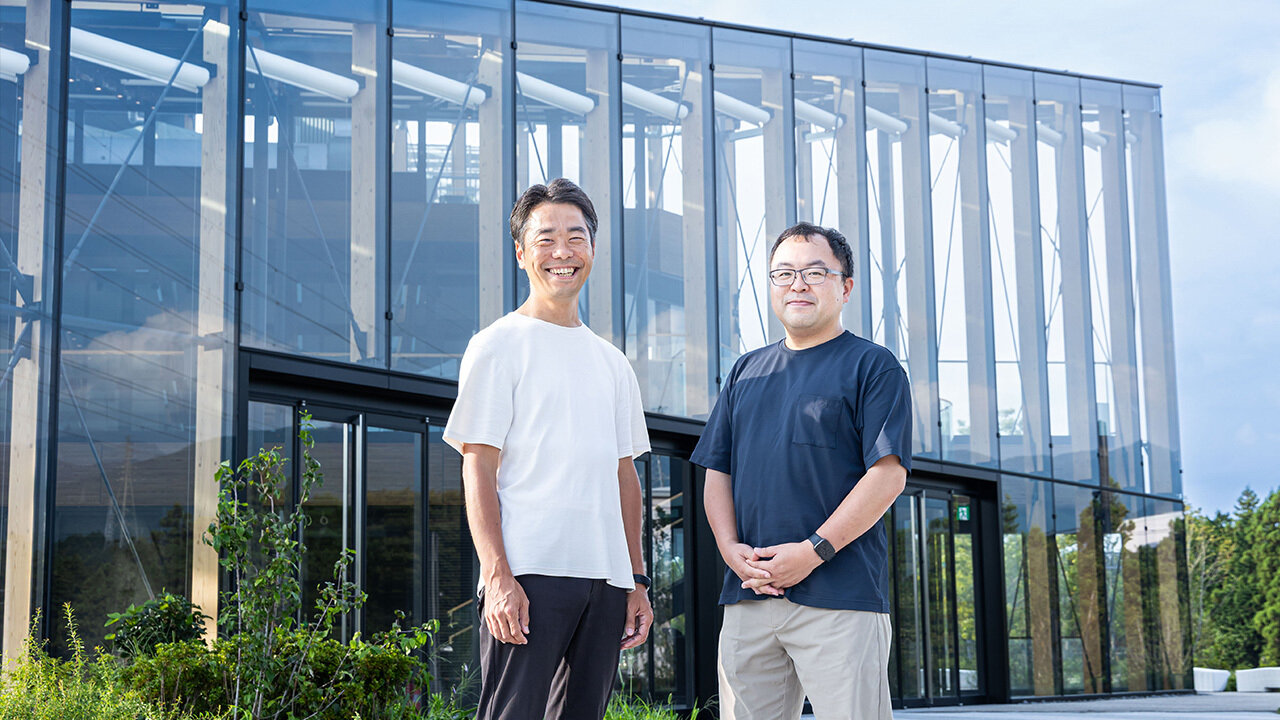
8月25日、ウーブン・シティのHPに「『Toyota Woven City Challenge ― Hack the Mobility ―』ページを公開」というニュースが掲載された。
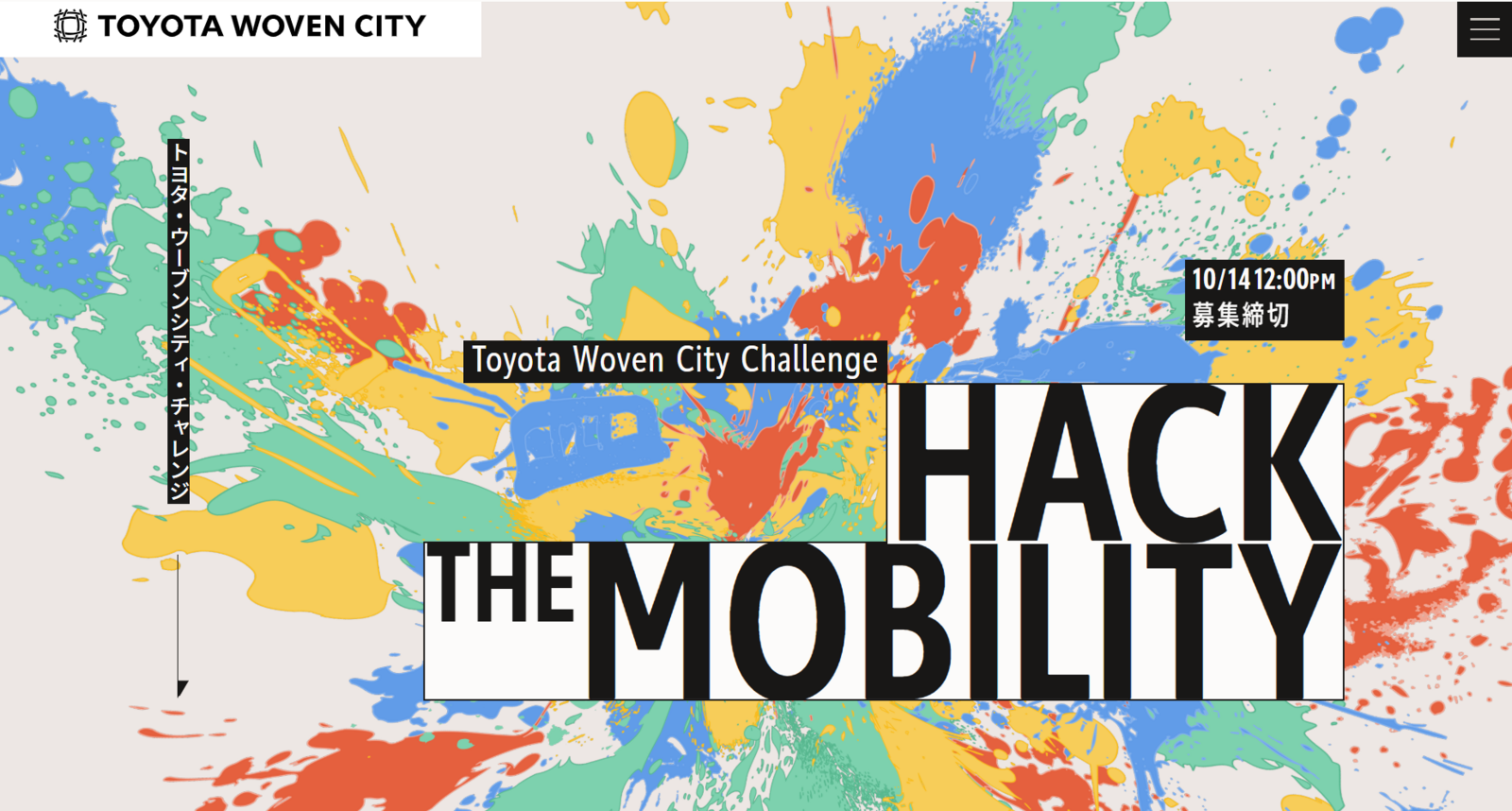
内容を見てみると、「一緒に未来を発明する仲間を募集」、「概ね創業15年以内」、「Woven City各種施設とサービス利用権」といった言葉が並ぶ。
「ウーブン・シティに備わる、さまざまなアセットを使い尽くしてほしい」。そんな想いで始まった、スタートアップを中心とする新たな発明家たちの募集。担当者に話を聞いた。
ウーブン・シティ3つのメリット
この連載の初回でも紹介したが、ウーブン・シティでは、実証実験に取り組む企業や個人の発明家をインベンターズと呼ぶ。
1月のCESで最初のインベンターズ5社を発表。8月にはトヨタやウーブン・バイ・トヨタ(WbyT)、トヨタグループのほか、インターステラテクノロジズと共立製薬が加入。9月1日時点で19社の参画が決まっている。
「Toyota Woven City Challenge」(以下、「プログラム」)では、この19社以外のインベンターズとして、よりスタートアップマインドの強い企業や組織、個人を募集する。選考は来年の春ごろまで。採択されれば、ウーブン・シティに集まる情報や施設、トヨタやWbyTの知見を活用して実証実験を行うことができる(最長18カ月)。
企業や自治体が主体となり、スタートアップを支援する取り組みには、一般的に「アクセラレータープログラム」と言われるものがある。こうしたプログラムと今回の「プログラム」の大きな違いは、採択された後に活用できるウーブン・シティの存在だ。
「プログラム」の企画内容をリードするウーブン・シティのコミュニティマネージャー・田中大裕さんが、「場所」「住民」「トヨタ」の3つの観点で説明してくれた。
田中さん

(公共の場所で)実証実験をやろうと思ったら近隣の住民との調整にも時間がかかることが多いですが、ウーブン・シティではその時間も比較的短くできます。
住民がいるということも大きい。(実生活から)切り離された場所で実験をしてみても、実際に使うかどうかわかりませんというパターンは多いです。実生活を送る住民がいて、使ってもらえるのはすごいところ。
3つ目はトヨタとのコラボレーション。
スタートアップや研究機関からすると、モノやサービスをつくっても、それを使ってもらったり買ってもらったりしないといけません。
「プログラム」では、トヨタやWbyTのアセットを使っていただけるので、実証したモノやサービスはトヨタにとっても連携できる魅力があります。
ただし、ウーブン・シティだからといって、無制限に実験できるということはない。安全安心、信頼、品質を維持するために守るべきルールはあるので、そこは注意が必要だ。
スタートアップの要望に応えつつ、安全安心のバランスを保つ。これは簡単なことではない。だが田中さんは「大事なところ」と言葉に力を込める。
「スタートアップにとって『面倒くさいこと』とするのではなく、世の中に出ていくときには、同じような品質が必要とされるので、WbyTがサポートやアドバイスさせていただく。世の中に出していくための基準とかプライオリティを示していくという価値になるかなと思っています」
世界を変えていくタッグ
ウーブン・シティに集まるスタートアップらに「できるだけ幅広くわがままを言ってほしい」。そう語るのは、「プログラム」の責任者であり、インベンター向けの開発、サポート、サービスのマネジメントをする大槻将久さん。

先述した通り、今回の「プログラム」ではウーブン・シティに集まるデータや施設、e-Paletteといった車両など、さまざまなアセットを使えることが最大のメリット。
一方でウーブン・シティもまた、フェーズ1のオフィシャルローンチを迎えるところ。今後、こうしたアセットも含めてテストコースの機能を段階的に強化、拡大していく。
街全体がテストコースという世界でも類を見ない取り組みには、何が必要か、何が重要か、大槻さんたちにとっても手探りだ。
その際に、インベンターズの“わがまま”は重要な“参考意見”になる。
ウーブン・シティのアセットをフル活用してもらい、改善点を教えてもらう。「私たちがそれに対して対応できるかどうか、ケイパビリティ(能力、組織力)も試されていると思っています」という。
「アクセラレータープログラム」には、一般的にスタートアップの取り組みを「加速させる」、「後押しする」というニュアンスが含まれる。ただウーブン・シティの「プログラム」では、それ以上にスタートアップと伴走する、一緒に取り組む意識が強い。
大槻さん
一般的に「アクセラレーター」とは、スタートアップが頑張っていこうとするのをアクセラレーションするということ。
私たちはタッグを組んで、「一緒に世界を変えていこう」という話なので、「(支援金や場所だけ提供して)いってらっしゃい」ではありません。
「プログラムや実証実験が終わったらそれまで」ではなく、ずっと一緒に走っていく仲間を見つけていこうということです。
スタートアップは「時間感覚とか、カルチャーが全然違う」と語る大槻さん。「その人たちと一緒に同じ目標に向かっていかなければいけない。私たちにも相当な覚悟をもって応募者の方々と向き合っていきたいと思います」と決意をのぞかせた。
